彼はパントマイムを“芸術”にした――
【終映日:2023年11月10日(金)】
【原題】L'art du Silence
【監督】マウリッツィウス・スタークル・ドルクス
【キャスト】マルセル・マルソー,クリストフ・シュテルクレ,アンヌ・シッコ,カミーユ・マルソー,オーレリア・マルソー,ルイ・シュバリエ,ロブ・メルミン,ジョルジュ・ロワンジェ,ダニエル・ロワンジェ
2022年/スイス=ドイツ/81分/パンドラ/DCP
|
10月28日(土)〜10月29日(日) |
19:05〜20:35 [レイト] |
|---|---|
|
10月30日(月)〜11月02日(木) |
16:30〜18:00 |
|
11月03日(金) |
19:05〜20:35 [レイト] |
|
11月04日(土)〜11月10日(金) |
10:00〜11:30 |
| 一般 | 大専 | シニア | |
| 通常 | ¥1,800 | ¥1,500 | ¥1,200 |
| 会員 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| 一般 | 大専 | シニア | |
| 通常 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| 会員 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
“パントマイムの神様”マルセル・マルソー。ボロボロのシルクハットと赤いバラ、白塗りメイクで世界に知られる道化師“ビップ”(BIP)。言葉をひと言も発せず、身ぶりと表情だけですべてを表現するマルソーの舞台はいかにして生まれたのか?第二次世界大戦中、フランスのレジスタンスに身を投じ、ユダヤ人孤児300人余をスイスに逃がしたマルソー。危険な状況下で声を発さないコミュニケーション方法は、戦後独自の芸術表現に昇華され国境を越えて広く愛されるようになった。
マルソーと共にレジスタンスに参加した従弟、彼の遺志を継ぐ家族、ろうの世界的パントマイマー、クリストフ・シュタークルら、マルソーを知る人物が登場し、彼の魅力を語る。沈黙の表現がなぜ人びとを惹きつけ続けるのか?豊富なアーカイブ映像を織り交ぜ、様々な視点からマルセル・マルソー、そしてパントマイムというアートの神髄に迫るドキュメンタリーである。
▶作品概要
マルセル・マルソーのアーカイブ映像から本作は始まり、マルソーの娘であるカミーユ・マルソー、オーレリア・マルソー、妻のアンヌ・シッコらがマルソーの人物像や思い出、家庭での姿を語る。アンヌ・シッコは自らパントマイムの教室の運営者でもあり、「いつかマルソーについての作品を作りたかった」と語る。家族で一つのパフォーマンスを練習する風景も映し出される。マルソーの孫、ルイ・シュヴァリエは「僕が5歳のときに亡くなったから 祖父のことはあまり知らない」と語るが、彼もまたダンスを学ぶ16歳のパフォーマーである。〈マルセル・マルソーの孫〉として見られることへの重圧を感じ、自分のスタイルを創りだそうと悩む。
インタビューから浮き彫りになるのは、ユダヤ人精肉店に生まれ、アウシュヴィッツで父を殺されたという、マルセル・マルソーのバックグラウンドだ。青年期、マルソーと共にレジスタンス運動に身を捧げた、108歳になる従兄弟のジョルジュ・ロワンジェ。ロワンジェの息子ダニエルが、ユダヤ人孤児300名余をスイスに脱出させたマルソーの抵抗の精神を詳細に語る。
また、マルソーを知る二人のパフォーマーが〈音のない芸術〉を語る。ロブ・メルミンは、マルソーのマイム学校で学び、世界的に知られるようになったが、パーキンソン病に罹患して以降、パントマイムやサーカスの技法を応用し、運動スキルをトレーニングする方法を研究・開発している。本作ではそのワークショップの模様が映し出される。また、ろう者のパントマイマーであるクリストフ・シュテルクレは、生来全く聴こえないが「その代わりマイムがあった」「聴覚はないが二倍激しく生きている」と手話で語る。シュテルクレは監督自身の父親であり、監督が映像に大きな関心を持つきっかけとなった。このようにして、“パントマイムの神様”、マルセル・マルソーの実像、そして〈沈黙の芸術〉が映し出されていく。









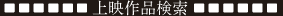

月例イベント

ブログ
